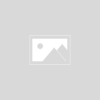一部上場サラリーマンが直面するリスクをSWOT分析してみよう!
現在、私はフリーランスのコンサルタント(アラフィフ)です。
昔はコンサルティング会社に勤務していましたが、うつ病で退職を余儀なくされ、40代で独立・起業の道を選択しました。
会社員時代は、ほぼ毎日仕事に追われていました。
ところが、フリーランスとなった現在は、契約に基づき、週3日程度の仕事をしています。
”半分働き、半分休む”
ようなイメージです。
その分、副業である金融投資や不動産投資にも力を入れることができるようになりました。
社畜でもなく完全リタイアでもない、その中間段階とも言える、この働き方(セミリタイア)こそが、私にとって最適なものなんだと確信しています。
そんな中、多くの会社員にとって、役に立ちそうな記事を見つけました。
私がいつも拝読しているkasaさんのブログです。
今回は、kasaさんのブログ記事のひとつを紹介させていただきたいと思います。
kasaさんのプロフィール
まず、kasaさんのプロフィールから見ていきたいと思います。
年齢
アラサーです。ギリギリ手前です。
家族構成
1歳ちょっとになる息子と妻との3人暮らしです。
学歴
理系の大卒です。いや〜大学まで出してくれた親には感謝です。
息子も大学に行く意思があるのであれば、金銭面では困らせたくないと思っています。
勤め先について
東証一部上場企業のメーカー系ですね。
kasaさんは、アラサーということですので、アラフィフの私とは約20歳の年の差があります。
にもかかわらず、20代サラリーマンの資産運用・節約術として、FIREを目指すブログを運営されています。
長期的な視点で、体系的に整理された、とても綺麗なブログです。
FIRE・金融投資・NISA・節約術のテーマなどの情報も多く、ブックマークしておきたいサイトのひとつだと思います。
kasaさんによるご自身のSWOT分析
SWOT分析とは、企業が戦略や今後の方向性を整理するときに使うフレームワークです。
S(強み)とW(弱み)、O(機会)とT(脅威)の4つの枠に当てはめて、今後の方向性を検討するものです。
FIREを目指すサラリーマンであるkasaさんは、ご自身のSWOT分析をしたものを記事にされています。
ひとつひとつ順番に見ていきましょう。
S(強み)
まずはS(強み)です。
やっぱりなんといっても強みはよほどヘマをしない限りは基本的にはクビにならないということだと思っています。企業によると思いますが、うちの会社では仕事ができない人ほど簡単で責任のない仕事を任され、ただ昇給はしっかりさせる。という素晴らしい環境が整っています。
これって日系企業あるあるかもしれませんが、仕事ができる人が損をする構図になってますよね。笑
会社員としての安定感を挙げられており、まさに同感です。
おじさん視点で少し付け加えると、会社員は想像以上に信用という強みがあります。
このため、会社を辞めてしまうと、口座開設・クレジットカード発行や各種ローンを組むことが困難になります。
会社を辞める前に「信用」という会社員特権の利用を済ませておくといいと思います。
W(弱み)
次にW(弱み)です。
真っ先に思い浮かんだのは”転勤・海外赴任”ですね。特に我が家は転勤してしまった場合、妻が会社を辞めなくてはならないので、その分世帯年収が下がることになってしまいます。。。それに息子も転校が必要になってしまいます。
そもそもですが、妻にも人生がありキャリアがあるわけで、旦那の都合で会社を辞めなくてはならない・・・が事実となってしまった場合、妻に申し訳ない気持ちが大きくなると思っています。
単身赴任よりは家族帯同がいいですが、やっぱり転勤も海外赴任もないのが一番ですよね〜。
会社に勤務する以上、その会社のルールに従う必要があります。
この管理不能なルールによって、ライフスタイルの変更を余儀なくされるのは辛いですよね。
こうなった場合にも対処できるよう、会社以外の収益源という視点が必要となってくるのでしょう。
会社以外の収益源さえあれば、減給することで出張を断ったり、奥様の退職分もカバーできるかもしれません。
この点、フリーランスは管理不能なものは少なく、自由に好きな仕事をすることが可能です。(その代償が不安定な収益です。)
O(機会)
次にO(機会)です。
サラリーマン(メーカー勤務)における今後の機会としては、東南アジアやBRICSに代表される先進国以外の成長が考えられると思います。日本以外の国が発展し、自社の製品の販売機会が拡大すれば自社によっても好機会が訪れるはずですよね。
あとは環境問題に対してどう取り組むのか?という観点も必要かもしれません。
SDGsなんて言葉もよく耳にするようになりましたが、本業のモノのクオリティや価格だけでなく”環境目線でどうなのか?”という観点も必要ということです。つまり、これまで製品を作る上での製造コストは安ければ安いほど良いとされていましたが、それと同じように”環境に良い生産工程になっているか”が重視されるということです。
環境はもちろん大切だとは思いますが、企業にとってはリスクとして考えてもいいと思っています。1万円で売れていたものが環境を意識した結果、製造コストが上がって1万1千円にせざるを得ないなんて状況も出てくるはずです。
社会・会社としては機会ですが、個人でみると海外転勤、給料低下にもつながるという点についても言及されています。
業種・業界によって異なりますが、グローバル化やSDGsの波を避けては通れないでしょうね。
これをT(脅威)ではなく、O(機会)として捉え、前向きに乗り切っていくことが重要なのでしょう。
T(脅威)
最後にT(脅威)を見ていきましょう。
生産効率の高い外国メーカーの参入や、自動車でいけば日系メーカーが得意なガソリン・ハイブリット車から、日系メーカーが不得意な電気自動車への変化あたりも挙げられるかと思います。
特に2つ目の電気自動車への変化については、トヨタの豊田章男社長も”電気自動車を走らせるための電気を火力発電で賄っており、結果的には電気自動車よりハイブリット車の方がCo2排出量が少なく環境に良い。環境に悪い電気自動車を普及させる前に発電方法から見直す必要があるのでは?”といったことを仰っていましたよね。(記憶を頼りに書いているので、間違いがあればごめんなさい。。。)
各国の思惑としては自国の産業を最優先したいわけですから、他国からの輸入車なんて買いたくないわけです。
とはいっても日本車の関税を爆上げするぜ!なんてことは言えないわけで、日系自動車メーカーが出遅れている電気自動車を普及させることで、他国の自国産業を伸ばす意図があるのでは・・・なんてことも言われています。
さすが、一部上場メーカー勤務といった視点です。
市場全体が縮小するという点については、結果として雇用にもつながり、本当に脅威だと思います。
あと、個人視点でのT(脅威)といえば、やはり、病気・怪我・死亡などのリスクです。
若い頃は、あまり意識することが少ないかもしれませんが…。
規則正しい生活・偏りのない食事・適度な運動…
など、肉体・精神を入念にメンテナンスしていたとしても、病気などはやはり限界があります。
私の場合は、突然の精神疾患でした。
死亡リスクは、生命保険や住宅ローンの団信などでカバー。
病気・怪我などは、医療保険・傷病手当金・障害厚生年金などでカバー。
私が一番重く感じているのは、
”生きているけど、長期的に働けなくなるリスク(家族含め)”
です。
所得補償、収入補償などの損害保険もありますが、意外に保険料も高く現実的ではありません。
まだ若いうちであれば、リスクは低いため、不動産投資など長期的な視点で不労所得を構築することが重要ではないかと思われます。
まとめ
kasaさんは、最後を次のように締めくくっています。
今回はサラリーマンとして働くことのリスクについてまとめてみました。
やっぱり転勤や海外赴任、給料が今のまま維持される保証がない等々、一生安泰なんてサラリーマン生活は存在しないことが改めてわかりました。このリスクがあることがわかった今、転勤や海外赴任をしないためには何が必要なのか・・・給料を上げるためには何が必要なのか・・・と考える必要があることも改めてわかりました。
10年後のFIREを目指すことが第一ですが、その間の10年間も本気でサラリーマンをやり続けたいと思います。
長期的な視点でよく考えられているなぁ
と感じました。
特に
「FIREまでの10年間も本気でサラリーマンをやり続けたい」
という点については、まさに同意です。
本当に重要なことだと思います。
私も週3日だけ働く生活をしていますが、その最初のステップが
”本業を大切にすること”
でした。
<<参考>>
本業でのスキルアップを怠れば、FIRE後のリスクヘッジも弱くなりますし、副業に良い影響を与えることも少ないと言われています。
現在は、FIREブームです。
ほとんどの書籍が、FIREするまでのステップについて多く言及しています。
もちろん、FIREまでの道筋は、誰もが知りたいことなのでいいんですが、私はさらに、次の2点が重要なのではないかと考えています。
・FIREした後に何をしたいのか(ダラダラする、趣味に没頭する、田舎に帰る…)
・FIREした後のリスクヘッジ(FIRE後に病気になったら、FIRE後に資産を失ったら…)
ようは、起こりうる、さまざまな事象について、事前に考えておけば、いざというときに、想定の範囲内におさまり、慌てることがなくなるはずだということです。
この点、10年後のFIREを目指すkasaさんの今回の自分SWOT分析は、一石を投じています。
あなたも、ご自身の置かれている環境で、まずリスク把握、そしてSWOT分析をしてみませんか。